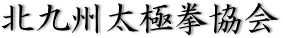
拳論・拳経
中国の清代に作られた太極拳の理論書、王宗岳(おう そうがく)の「太極拳論」や、武禹襄(ぶ うじょう)らによる一連の著作が、後に再整理され「太極拳譜」と総称されるようになりました。
修行の指針となる考え方(教訓)が多々書き記されています。
「太極拳論」あるいは「太極拳譜」のことを、「太極拳経」と呼ぶこともあります。
立身中正(りっしんちゅうせい)
自分の体がいつも平衡と安定の保たれた状態にいること。
必ずしも立ち姿勢の時に限らず、いつも自分の体が片方に偏ることなく、天秤のようにバランスが取れ、前後左右からの小さな変化にも敏捷に対応できるように。
意気揚々として八方を支えることのできる、余裕を持った気楽な状態でなければなりません。
虚領頂勁(きょれいちょうけい)
太極拳における頭・首のあり方(内面的要求)を表す常用語。
"領"は首=頚部の意味もあるが、むしろ全体で一つの纏まった概念、即ち、[頂]の勁を[虚]で"領"(引率)する、と読みます。
心静かに、気力を充実させ、首〜頭部が軽く"無重力状態"になったように想像すること
(と共に、気持を落ち着かせ全身の安定状態を保つ)。
含胸抜背(がんきょうばっぱい)
「含胸」とは胸をつっぱらないで伸びやかにすること、「抜背」とは背中の皮を引き下げること。
胸と背中はともにゆったりとさせ、自然に伸びやかに保ちます。
胸は無理に突っ張ったり、縮めたりしない。背中は脊柱をまっすぐに伸ばし、肩甲部や広背筋部を左右に、下方に伸びやかに広げます(ただし、丸めて猫背にしない)。
沈肩墜肘(ちんけんついちゅう)
肩関節をゆるめて開き伸ばし、鎖骨は持ちあげず、肩をそびやかしたり、後ろに引いたり、前に突き出したりしない。
肘も自然にゆるめて沈め、腕を前に出している時は肘窩が上を(肘頭が下を)向くように。
肘頭が外側に張ったり、肘を突っ張ったり、曲げ過ぎたりしない。肘を後ろに引き過ぎると、肩が容易にあがってしまう。
柔緩均一(じゅうかんきんいつ)
太極拳の動作が柔らかく緩やかでむらが無いという意味。
太極拳はゆっくりとした動作を主とし、「柔」と「緩」は太極拳の動作の特徴です。
勁を用いる時は綿々として断えることなく、力はこわばらず、とどこおらず、速度が急に速くなったり急に遅くなることなく、
一定の平均速度(等速運動)を保ちます。
用意不用力(よういふようりき)
太極拳の特徴は「意をより多く用い、力をできるだけ使わない」ことによって勁力(ちから)を得る点にあります。
太極拳は身体の外形・内面双方の意味での全身運動、すなわち、意識・動作・呼吸の一致した運動です。
太極拳をする時は、気持ちを落ち着けると同時に楽にし、全身をリラックスさせ、余分な力は使わないで行います。
上下相随(じょうげそうずい)
上半身と下半身がバラバラにならずお互いに影響し合うこと。
太極拳では「力は足から脚部、そして腰に伝わり、腰が主宰となり全身が定まる」と言い「一箇所でも動けば、全身が動く」とも言います。
腰を軸として胴体で四肢を導き、併せて手と足の動作と視線の変化を互いに調和させ、全身各部が止まらず連動してゆきます。
相連不断(そうれんふだん)
最初から最後まで、連綿不断で流れるように、全身が絶え間なく動きます。
動作から動作につながるとき、糸が切れたように停ったりとぎれたりしない。
一つの動作が終わりかけるころすでに次の動作が始まっています。
丁寧にメリハリをつけて動く中で、動きが静止しているように見えても固まることなくつづけてゆきます。